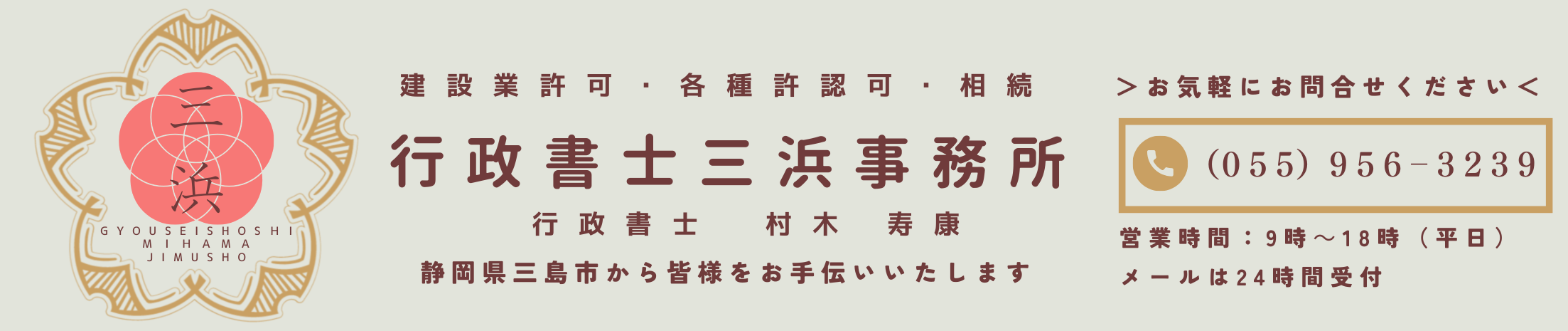相続・遺言書を行政書士に依頼するメリットは?行政書士に出来ること・できないこと
こんにちは、行政書士の村木です。
今回は、遺言書についてのお話です。
相続や遺言書の準備を考えたとき、「どの専門家に相談すればいいの?」と迷う方は少なくありません。
弁護士、司法書士、税理士、行政書士…それぞれ何が違うのか分かりにくいですよね。
実は、遺言書の作成サポートや相続手続きの書類作成には行政書士が適しているケースが多くあります。
特に費用を抑えながら専門家のサポートを受けたい方にとって、行政書士は心強い味方です。
この記事では、行政書士が相続・遺言でできること・できないこと、他の専門家との違いなどを分かりやすく解説しています。
目次
行政書士が「遺言・相続」で出来ること・できないこと
まず行政書士が相続・遺言の分野で「何ができて、何ができないのか」を見ていきましょう。
行政書士ができる業務
1. 遺言書の作成サポート(文案作成・助言)
行政書士は、遺言書の文案作成や書き方の助言を行います(後述しますが代筆はできませんので、あくまでサポートです)。
遺言書が法的に有効となるためには、民法で定められた形式要件を満たす必要がありますが、専門知識のない一般の方が作成すると不備が生じやすいのが実情です。
行政書士ができること
- 遺言の内容についてのヒアリング
- 法的に有効な遺言書の文案作成
- 自筆証書遺言の書き方指導
- 遺言内容の法的チェック
遺言書そのものを代筆することはできません。自筆証書遺言は本人が、公正証書遺言は公証人が作成するものだからです。
専門家のサポートって、本当に必要?
「代筆はしてもらえないのか」「遺言書なんて、自分で書けばいいのでは?」と思われるかもしれません。
実際、60歳以上の3割以上が「遺言書を作成したい」と考えているというデータがあります(総務省調査)。
しかし、令和5年度の統計によると実際に遺言書を作成しているのは全体のわずか9%{(公正証書遺言 + 検認件数) ÷ 死亡者数 = 遺言書作成率}程度です。
「作りたいけど作れていない」人が圧倒的多数なのです。
その理由の一つが「自分で書いて不備があったらどうしよう」という不安です。 実際、遺言書には厳格な形式要件があり、わずかなミスで無効になることがあります。
無効事例
ケース1:日付を「令和5年3月吉日」と記載 → 無効:日付が特定できないため、遺言書全体が無効に。
ケース2:パソコンで本文を作成 → 無効:自筆証書遺言は全文手書きが必須。(財産目録はPCでもOK)
ケース3:「夫婦で同じ用紙に一緒に遺言を書けば便利」と夫婦で共同作成 → 無効: 民法975条で共同遺言は禁止。
ケース4:不動産の表記が曖昧 → 手続き不可:「自宅」だけでは不動産を特定できず、相続登記ができない。
これらの失敗は、「事前に専門家のチェックを受けていれば全て防げた」ものです。
さらに深刻なのは、遺言書がないことで起きるトラブルです。年間約13,000件以上の相続が、遺産分割で揉めて裁判所に持ち込まれています(最高裁統計)。
しかも、その75%は遺産額5,000万円以下の「普通の家庭」です。「うちは財産が少ないから大丈夫」ということではありません。
行政書士のサポート費用で、家族の争いと高額な紛争解決費用を防げる――。
これが、行政書士サポートが必要な理由ともいえるでしょう。
2. 公正証書遺言の証人
公正証書遺言を作成する際には、証人2名の立ち会いが法律で義務付けられています。行政書士はこの証人を務めることができます。
親族(配偶者・子どもや孫)や利害関係者は証人になれないため、専門家に依頼するケースが一般的です。
3. 遺産分割協議書の作成
「もし遺言書を作らずに亡くなったら、どうなる?」というところに関係してくるのがこの「遺産分割協議書」です。
遺言書がない場合、相続人全員で「誰が何をどのくらい貰うか」を話し合う「遺産分割協議」を行います。
この協議で決まった内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」になります。
行政書士は、この遺産分割協議書の作成を代行できます。ただし、すでに分割内容が決まっている場合に限ります。
相続人全員が分割内容に合意している → 行政書士が書類作成
相続人間で意見が対立しており解決が困難 →行政書士では対応できないため弁護士が必要
遺言書があれば遺産分割協議は不要です。生前に法的に有効な遺言書を作成しておくことで、家族の手間や揉めるリスクを減らせます。
- なぜ揉めている場合は行政書士が対応できない?
-
行政書士は「書類作成の専門家」であり、相続人間の交渉や調整、紛争解決はできないからです(法律で禁止されています)。
そのため、当人同士での解決が難しい場合には弁護士に依頼して調停や訴訟で解決する必要があります。
相続人同士で対立が起きれば、解決のための手間もかかりますし、話し合いで解決できないと新たに弁護士を依頼するコストもかかります。
また法的に解決できたとしても、遺産を巡る争いで家族の絆が壊れ疎遠になってしまう可能性も否定できません。
遺言書は、それらのリスクから家族を守る「最後の思いやり」といっても過言ではないでしょう。
4. 相続人の調査(戸籍収集)
次に、実際に相続手続きが必要になった場合です。
相続手続きでは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定する必要があります。
この戸籍収集は、本籍地が転々としている場合には複数の役所に請求する必要があり、非常に手間がかかります。
行政書士はこの戸籍収集を代行し、相続人関係説明図を作成できます。
一般的な戸籍収集の流れ
1. まず、最後の本籍地(死亡時)の役所で戸籍を取得
2. その戸籍に記載されている「前の本籍地」を確認
3. 前の本籍地の役所に請求
4. さらに前の本籍地を確認
5. これを出生時まで繰り返す
本籍地の変遷が事前に分かっていれば複数の役所に同時に請求することも可能です。
しかしほとんどの場合、本籍地の変遷を正確に把握していないことが多いため、順番に遡る必要があります。
5. 相続財産の調査
相続財産の調査については、遺言書作成時(生前)と相続発生後の両方で必要です。
被相続人の財産を把握するため、預貯金、不動産、有価証券などの調査を行うのが相続財産の調査です。
行政書士は、金融機関への残高証明書の請求や、財産目録の作成を代行できます。
-
なぜ遺言書作成時にも相続財産の調査が必要?
-
「何を誰に相続させるか」を書くには、財産リストが必要です。財産を把握していないと、遺言書に書き漏らしが起きるケースも存在します。
遺言書に「自宅と預金を長男に」と書いたが、 実は株式や別の銀行口座があったことを忘れていた
→ 書き漏らした財産は遺産分割協議が必要に
また、遺言書があってもなくても相続税の申告には財産目録が必要になります。遺言書に書かれていない財産の確認・相続人への財産の引き渡しなど、財産の全容把握が必須です。
6. 遺言執行者業務
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。遺言書で指定されていれば、行政書士も遺言執行者になることができます。
つまり遺言執行者は「生前に決めて、死後に動く」位置づけです。
遺言執行者の主な業務
- 相続財産の管理
- 預貯金の解約・名義変更
- 有価証券の名義変更
- 相続人への財産の引き渡し等
遺言執行者が指定されていないと、金融機関から相続人全員の同意書・戸籍謄本・実印・印鑑証明書等を求められるケースがあります。
7. 預貯金・有価証券・車両の相続手続き
不動産以外の相続財産については、「相続人全員が合意している状態」であれば、行政書士が名義変更や解約手続きをサポートできます。
行政書士ができない業務
1. 不動産の相続登記
不動産(土地・建物)の名義変更である相続登記は、司法書士の独占業務です。行政書士は対応できません。
相続財産に不動産が含まれる場合は、司法書士への依頼が別途必要になります。
2. 相続税の申告
相続税の計算や申告書の作成は、税理士の独占業務です。
相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、税理士への依頼が必要です。
3. 相続トラブルの訴訟代理
前述していますが、相続人間で争いが生じ調停や訴訟に発展した場合の代理人業務は、弁護士の独占業務です。
すでにトラブルが起きている場合は、最初から弁護士に相談することをおすすめします。
4. 遺言書検認の書類作成
自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です(法務局保管制度を利用した場合を除く)。
この検認手続きの書類作成は、家庭裁判所に関わる業務であるため、行政書士は対応できません。
行政書士への相談が向いているケース
行政書士は、相続・遺言の分野で以下のような方に特におすすめです。
費用を抑えて専門家のサポートを受けたい方
他の士業に比べて料金が安く、コストパフォーマンスに優れています。
トラブルなくスムーズに遺言書を作りたい方
法的に有効な遺言書を作成できます。
相続人調査など煩雑な手続きを任せたい方
戸籍収集などの面倒な作業を代行してもらえます。
まずは気軽に相談したい方
初回無料相談を実施している事務所が多く、気軽に相談できます。
一方で、以下のケースでは他の専門家が適切です。
不動産の相続登記が必要 → 司法書士
相続税が発生する → 税理士
すでに相続トラブルがあり、相続人同士での解決が困難 → 弁護士
大切なのは、自分の状況に合った専門家を選ぶことです。
遺言書は、残される家族への最後のメッセージです。専門家のサポートを受けて、確実で有効な遺言書を作成しましょう。
無料相談やお問い合わせはこちらから
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
補助者→使用人行政書士→個人開業(令和5年10月開業)
真面目で誠実な対応を心掛けています。
最新の投稿
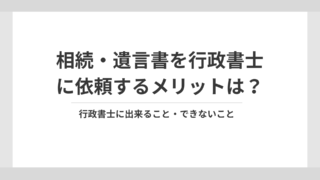 お知らせ2025年11月1日相続・遺言書を行政書士に依頼するメリットは?行政書士に出来ること・できないこと
お知らせ2025年11月1日相続・遺言書を行政書士に依頼するメリットは?行政書士に出来ること・できないこと お知らせ2025年7月2日終活セミナーを行いました
お知らせ2025年7月2日終活セミナーを行いました お知らせ2024年11月18日三島市の申請取次行政書士です。
お知らせ2024年11月18日三島市の申請取次行政書士です。 お知らせ2024年9月2日著作権と行政書士
お知らせ2024年9月2日著作権と行政書士